必要な資金繰りサービスはどっち?
▼ 入金を"早める"!
おすすめのファクタリング会社
▼ 出金を"遅らせる"!
請求書をカード払いに切り替え
資金ショートとは
資金ショートとは、会社の手元資金が足りなくなり、支払いができなくなる状態のことです。
「倒産」とまではいかなくても、いま払うべきお金がない状況を指します。
たとえば、商品・サービスを売っていて売上はあるのに、入金が遅れていたり、かなり先になる場合。
その間にも、仕入れ代や給料、家賃の支払い日がやってきます。
手元に現金がなければ、どれだけ利益が出ていても支払うことができません。
つまり、黒字でも資金ショートは起こるのです。
これは「黒字倒産」と呼ばれることもあります。
また、資金ショートは一時的な現象でもあります。
1週間だけ資金が足りない、ということもあれば、何か月も資金不足が続くケースもあります。
いずれにせよ、支払いが滞れば経営に大きな影響を与えるのはまちがいありません。
この状態が長く続けば、取引先や金融機関との信頼が崩れ、やがては倒産につながることもあります。
資金ショートになる原因
資金ショートが起きる原因は、一つではありません。
会社の資金繰りにまつわる複数の要素が重なって起こります。
入金と支払いのタイミングのズレ
最もよくあるのが、売上の入金より支払いが先にくることです。
たとえば、「月末締め・翌々月払い」で売上が立っている場合、実際にお金が入ってくるのは2か月後です。
一方、仕入れ代金や人件費は、売上を計上したその月や翌月に発生することが多いです。
このズレによって、キャッシュが回らなくなります。
とくに、取引先が大企業であるほど、入金条件が厳しく、支払いのサイト(タイミング)に開きが出がちです。
小さな会社ほど、「資金のタイムラグ」に耐えられる体力がないため、ショートしやすくなります。
売掛金の未回収・遅延
売上が立っても、売掛金が回収できなければ、会社にはお金が入ってきません。
請求書の発行ミスや、相手先の経営悪化などで回収が遅れると、予定していた資金繰りが崩れます。
とくに「締め日以降にまとめて請求」「担当者が休んでいて確認が遅れた」など、社内の運用ルールのあいまいさが原因になることもあります。
確認漏れのせいで未入金のままになることも少なくないので、売掛金は早めに請求し、入金管理も徹底するべきです。
固定費の負担が重い
家賃・人件費・保険料・リース代など、毎月発生する支出を「固定費」といいます。
この固定費が高いと、売上が下がった月でも支払いが減らず、資金ショートに直結します。
特に、スタッフを増やした直後やオフィス移転などのタイミングでは注意が必要。
固定費はすぐに減らせないことも多く、損益計算書では見えにくいリスクです。
在庫や先行投資の増加
事業拡大や新商品の準備で、仕入れを増やしたり、新しい設備を導入したり…
こうした先行投資が多くなると、お金が出ていくタイミングが早まり、現金が不足します。
収益化までに時間がかかると、キャッシュフローがさらに悪化します。
「資金に余裕があるうちに次の一手をうったが、思ったより集客が伸びず…」ということはよくあるので、注意が必要です。
経営判断ミスや外部環境の変化
過剰仕入れや設備投資だけでなく、急なキャンセルや景気悪化、コロナのような外的要因も影響します。
これらは防げない面もありますが、普段から「お金の見える化」をしていれば、早めに対応できます。
資金ショートが会社に与える影響
資金ショートが起きると、単に「お金が足りない」というだけでは済みません。
会社の信用、従業員、取引先、金融機関との関係など、あらゆる方面に悪影響が広がります。
支払い遅延 → 信用の低下
まず起きるのが、仕入先や業者への支払い遅れです。
一度支払いが遅れると、「この会社は大丈夫か?」と疑念を持たれ、仕入れ条件が厳しくなったり、最悪の場合は取引停止になることも。
さらに、その噂が他社へも広がるリスクがあります。
取引先が減れば、売上にも影響が出ます。
支払いが遅れるだけで、会社の信用は簡単に揺らぎます。
従業員への影響
資金ショートが続くと、給料や交通費、業務費の立て替え精算などに遅れが出ることもあります。
これらは社員の生活に直接影響するため、不満がたまり、モチベーションも下がります。
結果として、人材が離れていき、残されたメンバーの負担が増し、会社全体の生産性が落ちていきます。
中小企業ほど、ひとりの退職が全体に与える影響は大きいため、早めの対処が必要です。
銀行や金融機関の対応が厳しくなる
資金ショートを起こした企業は、金融機関からの信頼を失いやすくなります。
「資金計画が甘い」と判断されると、以下のような対応をとられることも。
- 追加の融資を断られる
- 返済猶予の交渉が難航する
- 条件変更の審査が通りにくくなる
- すでにある借入金の条件変更を求められる など
また、取引銀行に対して正直・正確に報告しなかった場合は、さらに信用が落ちます。
日ごろから金融機関と定期的に面談し、資金繰り表などを見せておくことが大切です。
二次被害 → 売上減・倒産リスク
仕入が止まれば、製品やサービスの提供ができなくなります。
すると、納期遅延やキャンセルが発生し、売上そのものが減っていきます。
このように、資金ショートは「連鎖的な問題」を引き起こし、気づいたときには抜け出せなくなっているケースもあります。
最終的には、黒字でも資金ショートによって倒産に追い込まれる企業もあるのです。
資金ショートしないための対策
資金ショートは、日々の資金管理と準備で予防できます。
以下のような対策を講じておきましょう。
資金繰り表を作る
未来の資金の流れを「見える化」するのが第一歩です。
- 今月の入金予定(売上・借入・補助金など)
- 今月の支払予定(家賃・給与・仕入など)
- 翌月以降の動きもざっくり予測
これをExcelなどで一覧にしておくだけでも、資金ショートの予兆に気づけます。
数字を見るのが苦手なら、簡単な出入り表(キャッシュフロー表)からでOK。
慣れてくると週単位、日単位でも管理できるようになります。
請求と回収を早める
請求書の発行を後回しにせず、なるべく早く送る習慣をつけましょう。
また、取引先と交渉して、
- 翌々月払い→翌月払いにしてもらう
- 締め日を月2回に変更する など
このような小さな改善が、キャッシュフローを大きく変えます。
さらに、入金確認のチェック体制を整えることも重要。
請求書を出して満足せず、入金までをしっかり追いましょう。
支払いをコントロールする
逆に、以下のような支払いを遅らせる工夫も重要です。
- 支払サイトを延ばしてもらえないか交渉
- 一括ではなく、分割払いにできないか提案
現金流出を後ろにずらすことが資金繰りの安定に役立ちます。
これらの調整は、相手との信頼関係があることが前提。
だからこそ、資金繰りが苦しいときだけ頼るのではなく、普段から相談しやすい関係性を築いておきましょう。
ムダな出費を見直す
ムダな出費のカットや、不要なものの現金化も有効です。
たとえば、
- 使っていないツールやアプリの月額費用
- 毎月頼んでいるけれど使い切れていない仕入れ
- 眠っている在庫や資産の売却 etc.
これらは「会社の当たり前」になっていることが多く、気づきにくい存在です。
定期的に支出の明細を見直して、なくても回るかもと思うものは、いったん止めてみてもいいでしょう。
緊急時の資金調達方法を知っておく
もしもに備えて、資金調達や資金繰りの手段・サービスを知っておきましょう。
- 借りる
(銀行や日本政策金融公庫の融資・ビジネスローンなど) - 早める
(ファクタリングなど) - 遅らせる
(請求書カード払いなど)
これらの方法を、資金ショートの前に準備しておくのがポイントです。
資金ショートしたときの復活方法
それでも資金ショートしてしまったら、そこからの復活に向けて速やかに行動しましょう。
1. 現状を正確に把握する
まず、「あとどれだけ持つか」を冷静に見積もる必要があります。
- 現金残高
- 入金予定
- 支払い予定
- 今週・今月の資金収支
ここが整理されていないと、正しい判断ができません。
2. 緊急の資金調達をする
現金が明らかに足りない場合は、以下のような調達手段を講じましょう。
- 公庫や銀行に融資を申し込む
- ファクタリングを活用する
- 借入枠があるなら即時引き出す
ただし、銀行や信用金庫からの融資は審査に時間がかかりがちで、普段からの信頼関係も重要なため、スピーディーな対応が難しいこともあります。
まとまった売掛金があるならファクタリング、なければ金利が少し高めになりますがノンバンクのビジネスローンの活用も検討しましょう。
3. 支払いを交渉して延ばす
全額を用意できなくても、「あと1週間待ってもらえれば払える」という状況であれば、取引先への相談が有効です。
支払い先に誠実・正確に説明し、以下のような対応を交渉してみましょう。
- 翌月支払いへの延期
- 一部だけの先払い
- 分割払いへの変更
一時的な資金難であれば、柔軟に応じてくれる取引先も多いです。
最近は、請求書を法人カードでの支払いに切り替えることで、出金をカードの締め日まで先延ばしにできるサービスもあります。
4. 不採算事業の見直し
資金が足りない状態では、すべてを守ることはできないこともあります。
利益が出ていない・今後も改善が見込めない事業は、思いきって縮小・撤退を検討しましょう。
- 毎月赤字のサービス運営
- 集客がうまくいっていない広告活動
- 人件費がかかるが利益が出ていない部署 など
会社のリソース(人・お金・時間)を広くうすく使うのではなく、生き残る部分にせまく深く集中させることが、
復活への最短ルートとなります。
資金ショートに関連する質問
資金ショートに関連する質問を紹介します。
必要な資金繰りサービスはどっち?
▼ 入金を"早める"!
おすすめのファクタリング会社
▼ 出金を"遅らせる"!
請求書をカード払いに切り替え







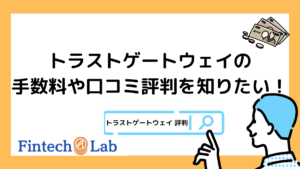

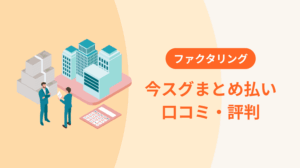

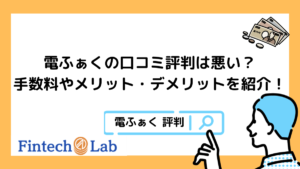


コメント